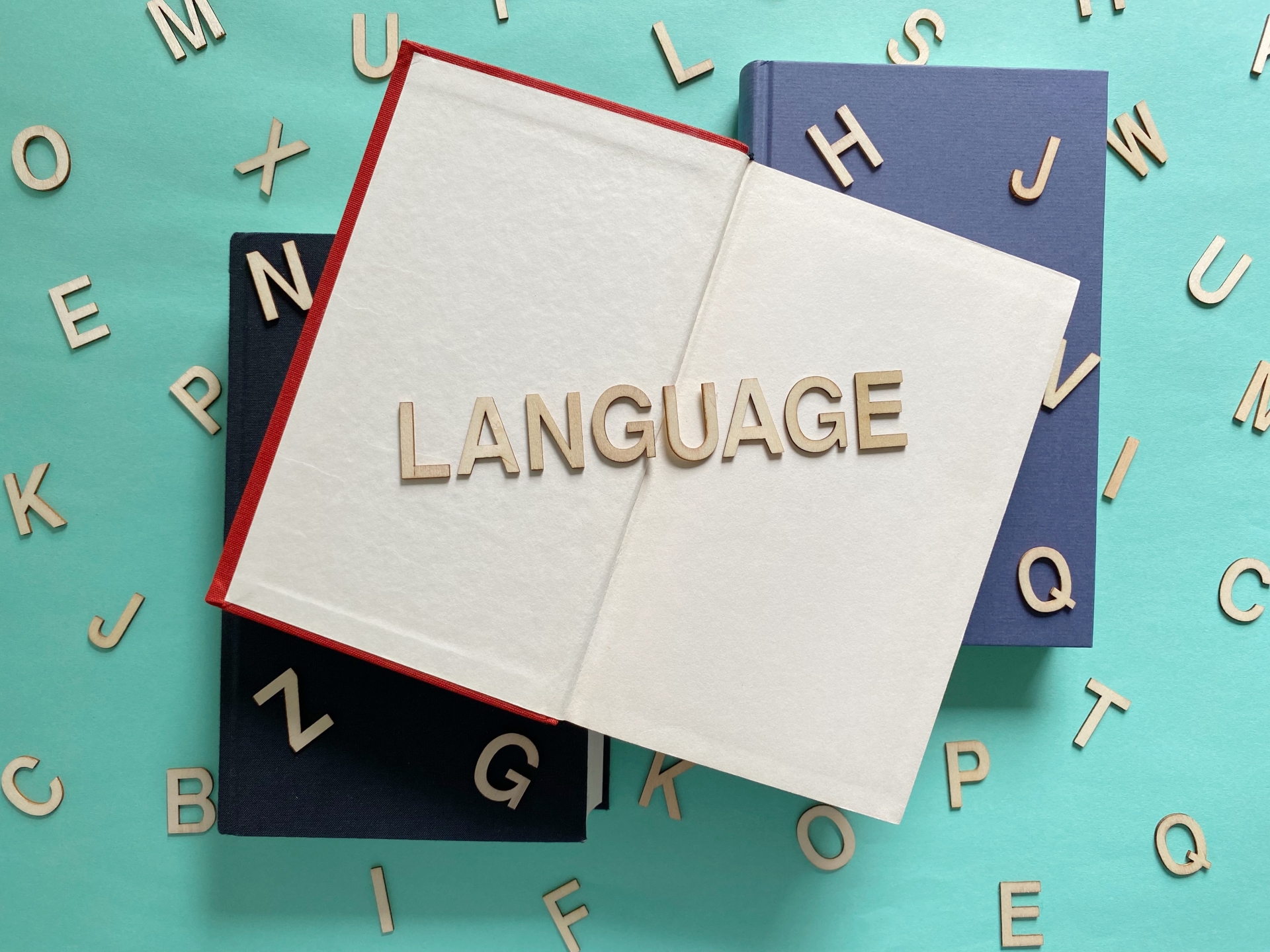客室稼働率(OCC)とは?ADR・RevPARとの違いや目安も解説
公開日 (更新日 2024.01.09)

ホテルの経営を安定させるためには、客室の稼働状況や利益を数値化し、各担当者が情報を共有することが必要です。このとき使えるのが、「客室稼働率(OCC:Occupancy Rate)」や「客室平均単価(ADR:Average Daily Rate)」、「レヴパー(RevPAR:Revenue Per Available Room)」といった指標です。
宿泊業界の指標としてよく使われるこれらの意味や、業界全体の客室稼働率の平均値、また客室稼働率を上げるコツなどを解説します。
目次
「客室稼働率(OCC)」の意味と計算方法
客室稼働率は、ホテルの経営状況を知るための基本的な指標です。概要とともに、計算方法についても解説します。
客室の稼働具合を測る指標
客室稼働率は、ホテルの客室が宿泊客に利用され稼働した割合を指す指標で、ホテル経営を考える際に重要だとされています。1日〜年単位での計算ができるため、一定期間内の客室の販売状況を見る際に有効です。
客室稼働率の数値が高ければ順当に部屋が埋まっていることになり、低ければ空室が多いことになります。夏休みやGWなどの大型連休シーズンには上がりやすい傾向です。
計算式は「稼働した客室数 ÷ トータルの客室数」
客室稼働率の計算は、以下の公式に当てはめて行います。
| 客室稼働率(OCC)=稼働した客室数÷ホテルのトータルの客室数×100 |
たとえば100室あるホテルで、30室利用がある場合の客室稼働率は(30 ÷ 100)× 100 = 30%となります。
ただし、客室稼働率はあくまでも客室がどの程度稼働しているかを見る数値です。実際の売上を見るものではないため、ホテルの収益が増えているかは分かりません。ホテルの経営状態を把握したいのであれば、以下に紹介する指標と併用する必要があります。
「ADR」「レヴパー(RevPAR)」とは?

ADRは「客室平均単価」を示す指標
ADRとは、客室平均単価のことです。その日、客室がいくらで売れたのかを示します。なお、販売チャネルの違いやキャンペーンの有無、客室タイプによる価格差などは考慮しません。
計算式は以下の通りです。
| 客室平均単価(ADR)=売上金額 ÷ 販売した客室数 |
1日10万円の売上で、4部屋販売した場合は100,000 ÷ 4 = 25,000となります。つまりこのホテルの部屋には、1日あたり2万5,000円の価値があることになります。
ただし、ホテル全体の収益までは把握できません。あくまでも1部屋単位での計算になり、1部屋の料金を考える際の基準に留まるためです。
レヴパー(RevPAR)は「1室あたりの収益」を示す
レヴパーは、販売できる客室1室あたりの収益を表す指標です。
レヴパーは、以下の計算式に当てはめて求めます。
| 1室あたりの収益(RevPAR) = 客室稼働率(OCC) × 客室平均単価(ADR) (または、総客室収益 ÷ 販売できる客室数) ※客室平均単価(ADR) = 売上金額 ÷ 販売した客室数 |
客室稼働率が30%、客室平均単価が2万5,000円の場合は、0.3 × 25,000 = 7,500となります。つまりこのホテルの場合、1室は7,500円の価値だと判断できるのです。
レヴパーが低い場合は客室料金の値下げ、高い場合は客室料金の値上げが考えられます。ただし、レヴパーでは経費などは算入していないため、実際の利益は判断できません。
その他のホテル経営に使える指標
上記で述べた以外にも、ホテルの経営状態を判断するための指標はあります。中でも活用されることの多い、「市場浸透率(MPI:Market Penetration Index)」や「平均料金指数(ARI:Average Rate Index)」、定員稼働率についてそれぞれ解説します。
競合施設と稼働率を比較する「市場浸透率(MPI)」
市場浸透率とは、自社のホテルの客室稼働率と競合施設やホテル業界の平均稼働率を比べることで、どの程度のシェアを獲得できているか、把握することができる指標です。
計算式は以下の通りです。
| 市場浸透率(MPI) = 自社のホテルの稼働率 ÷ 競合施設の稼働率×100 |
市場浸透率が100%になれば、適正なシェアだと言えます。数値が低ければ、料金設定に課題があり、うまくシェアを獲得できていないのかもしれません。一方、数値が高ければ、さらに宿泊料金を上げられる可能性が示唆されます。
競合施設の料金設定との差を測る「平均料金指数(ARI)」
「平均料金指数は、平均客室単価指数とも呼ばれ、競合施設の客室平均単価と比較し、自社のホテルの料金が競合より安価あるいは高価であるかを把握することができます。
求める際は、以下の計算式を利用します。
| 平均料金指数(ARI) = 自社ホテルの客室平均単価(ADR) ÷ 競合の客室平均単価(ADR) |
平均料金指数が1.00以上になる場合は競合より料金が高め、1.00以下になる場合は低めだと言えます。料金設定の参考になる指標ですが、ホテル業界全般の平均とは比較できません。あくまでも、競合との差を測るためのものとなります。
客室の利用状況がより正確に分かる「定員稼働率」
総収容人数に対しての、のべ宿泊者数の割合を「定員稼働率」と言います。客室稼働率は部屋ごとの稼働状況を測るものですが、定員稼働率は1部屋を利用した人数を基準にするものです。
客室稼働率より正確に、客室の利用状況が分かります。ファミリー層の多いホテルのように1部屋に泊まる人数が多い場合に、有効な指標だと言えます。
計算式は以下のようになります。
| 定員稼働率 = 一定期間ののべ宿泊者数 ÷ その期間の総収容人数 |
ホテル経営に指標を使う重要性

ホテル経営に指標を使うのは、自社のホテルの現状を正確に把握し、目標にどの程度近づいているかを測ったり、意思決定の指針にしたりするためです。
客室稼働率は、多くの要因で変動します。そのため、経営者の感情や勘に頼って判断してしまうと、経営が立ち行かなくなるおそれもあるのです。
客室稼働率(OCC)の平均と採算ラインは?
自社のホテルの稼働率を考える前に、まずは他社の状況も知っておきたいところです。客室稼働率の平均について統計を元に解説するとともに、採算ラインについても考えます。
客室稼働率の平均はコロナ禍突入前62.7%・突入後34.3%
観光庁によると、2021年度の日本の宿泊施設における客室稼働率は、日本全国で34.3%でした。施設別では、以下の通りです。
参考:観光庁『宿泊旅行統計調査(令和3年・年間値(確定値))』
- 旅館:22.8%
- リゾートホテル:27.3%
- ビジネスホテル:44.3%
- シティホテル:33.6%
なお、コロナ禍突入前の2019年は、日本全国で62.7%。施設別では、以下の通りでした。
参考:観光庁『宿泊旅行統計調査(令和元年・年間値(確定値))』
- 旅館:39.6%
- リゾートホテル:58.5%
- ビジネスホテル:75.8%
- シティホテル:79.5%
採算ラインの計算式
客室稼働率をアップさせ、利益を増やすためには、まず自社のホテルの採算ラインを知っておく必要があります。
ホテルの採算ラインを把握するには、損益分岐点売上高を求めましょう。損益分岐点売上高とは、売上と費用が同額で、利益がゼロとなる売上規模のことです。
損益分岐売上高を出すには、固定費の金額と限界利益率の数値が必要です。まず、費用を変動費と固定費に分けましょう。変動費は、以下のように売上が上がるほど金額が上昇する費用が該当します。
- 水道代
- 電気代
- 食材費
一方、固定費は以下を始め、ホテルの操業状態を問わず発生する費用が含まれます。
- 土地代
- 賃料
- 人件費
売上高から変動費を引いたものを「限界利益」、売上高の中で限界利益が占める割合を「限界利益率」と言います。計算式は以下の通りです。
| 限界利益率 = (売上高 - 変動費) ÷ 売上高 |
利益がゼロということは、固定費と限界利益の差がないことになります。以上を踏まえて、損益分岐点売上高の計算式はこの通りになります。
| 損益分岐点売上高 = 固定費 ÷ 限界利益率 |
損益分岐点売上高はホテルの業態・利益構造などにより大きく変わるため、一概にいくらを目指せば良いという指標はありません。
しかし宿泊業界は他の業界に比べると損益分岐点が高く、自社の状況を把握した上での経営が必須です。上記の式で割り出した数値を元に、施策の方向性を考えていくことをおすすめします。
客室稼働率(OCC)を上げる3つの方法
客室稼働率を上げ、利益を生み出す方法としては以下の3つが考えられます。
- 全ての客室を売り出す
- ホテルのリピーターを獲得する
- 固定費の削減やスタッフの生産性向上に努める
展望が良くないなどで売り出しづらい部屋は、「訳アリ」とうたってアウトレット価格にしましょう。直前の宿泊で安くなるプランや、性別・年代に特化したプランもおすすめです。ただし、プランを増やし過ぎるとユーザーを迷わせてしまうため、ある程度の数で収めましょう。
設備や料理、接客などあらゆる内容を分析し、リピーター獲得のために必要なことは何かも把握しましょう。リピーターは、特別な広告をしなくても泊まりに来てくれる貴重な存在です。その宿にしかないものを求める傾向があるため、自社のホテルの売りが何かを考えてみてください。
利益を生み出すためには、経費の削減も考えなければなりません。ホテルは人件費や固定費が高く、その削減やスタッフの生産性向上も重要です。自動化できる部分は自動化し、光熱費などを抑える工夫を考えてみてください。
アメニティを希望者だけに渡すといった、小さな工夫も大切です。こうした経費削減でできた余力を、新たな顧客サービス実施や宿泊料金の値下げに回し、客室稼働率(OCC)を上げるのも手です。
客室稼働率の改善に取り組む際の注意点

客室稼働率を上げるために、合わせて注意したい点も3つあります。
- 長い目で見て取り組む
- Webサイトの整備を抜かりなく行う
- 外国人利用客にも注目する
客室稼働率はすぐに上がるものではなく、1つの施策だけで効果が出るとも限りません。客室稼働率の改善には、長い目で見て取り組んでいくと良いでしょう。
また、Webサイトも細部まで作り込んでおきましょう。昨今のホテル予約はWeb経由が大半で、Webサイトが洗練されていないと、潜在顧客を逃してしまうおそれがあります。デザインだけではなく、サイトへユーザーを流入させるためのSEO(検索エンジン最適化)対策にも力を入れたいところです。
外国人利用者を呼び込むための施策として、ホテルの多言語対応も考えましょう。前述の観光庁の資料によると、コロナ禍突入前(2019年)における外国人宿泊者は1億人以上でした。
コロナ禍突入後は400万人ほどに激減したものの、2022年時点では回復傾向にあります。2022年度には、1,700万人近くに上っています。外国人利用客向けの対応もしておくことで、客室稼働率アップが見込めるでしょう。
客室稼働率アップには多角的な視点を持った経営を
客室稼働率を上げるのは簡単ではありません。客室の稼働状況や売上などをさまざまな指標で割り出し、課題を見つけて多角的に対応する必要があります。そのためには外部コンサルタントを頼ったり、経営セミナーなどに参加したりする方法もおすすめです。
旅館・ホテル専門 集客コンサルタントの株式会社宿力では、ホテル経営者向けのコンサルティングや経営セミナーを行っています。旅館・ホテル出身者、宿泊施設特化型IT企業出身者、Webエージェント出身者などが多数在籍。客室稼働率を上げ、利益を生む経営をサポートします。集客アップのコンサルティングは、宿力にお任せください。